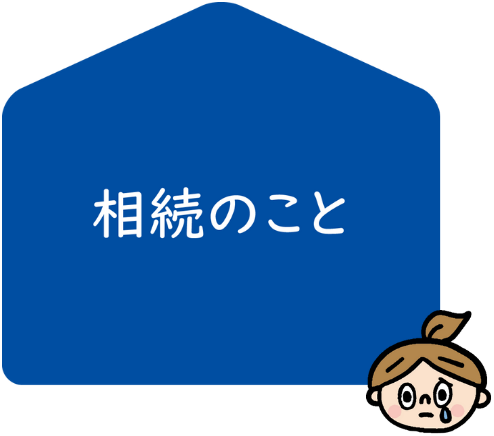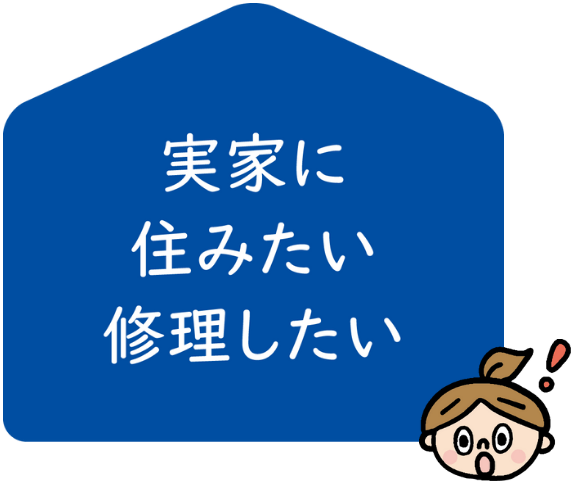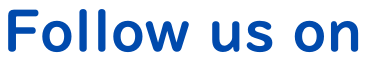ご相談から依頼までの流れ

①まずはお電話かメールにて
お問い合わせください。

②無料カウンセリング・ご相談は直接or
オンライン(PCやスマホ)でも可能です。

③内容に応じて専門家を
紹介したり、問題解決まで
スタッフがサポートします。
Q&A よくある質問
Q1. 空き家にしていたら何が問題ですか?
A.
空き家=問題ということではありません。適正に管理されずに放置されると、老朽化の進行が加速し、建物や工作物の倒壊・落下などを招き、人に危害を与えるリスクが高まります。また、防犯面(侵入・不法投棄・放火など)や、環境衛生上の問題(害虫など)も発生しやすくなることで、近隣トラブルに発展することも少なくありません。空き家の管理費用(固定資産税・火災保険・草刈りなど)の負担も発生します。このように、空き家を放置すればするほど、周辺環境や地域コミュニティにさまざまな悪影響が及びやすくなることが問題点とされており、2023年12月には改正空き家対策特別措置法が施行されています。
Q2. 空き家を相続したが利用する予定がない。どうすればいいの?
A.
住まいとして活用でき、需要もあるような地域であれば賃貸住宅として貸し出すのもよいのではないでしょうか。住宅は使われなくなると、老朽化が進行します。適切な維持管理を行わずそのままにしておくというのは一番の問題です。老朽化していてリフォームをしても活用が難しいような住宅の場合は解体を検討するのもひとつです。土地を保有するにも税金や維持管理(除草など)が必要です。利用する当てがない資産を保有し続けるよりも早めに売却した方が新しい転入者に期待でき地域にとっても望ましい場合もあります。 相続した空き家については、一定の要件を満たした上で譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除を受けることも可能です。また、更地として土地を所有した場合には、宅地と比べて固定資産税が6倍になることも考慮しておいてください。
Q3. 空き家管理はどこのエリアでも対応可能ですか?
A.
原則、糸島市・福岡市西区に限らせていただいておりますが物件やご希望に合わせて、作業内容や頻度を決めたうえで価格提示をさせていただいているので、まずはお気軽にご相談ください。
Q4. 介護保険のしくみや福祉施設の選び方など初めてのことばかりで全く分からない…。
A.
地域の介護情報探しの入口となるのが、「地域包括支援センター」です。地域包括支援センターは、地域の要介護者やその家族を総合的に支えるための機関で、全国に約7,000か所(サブセンター含む)設置されています。市区町村が直接運営しているものもありますが、多くは外部の社会福祉法人等に運営委託されています。
地域包括支援センターには主任ケアマネジャーや社会福祉士、保健師などの専門スタッフが配置され、要介護者の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行っています。また地域の医療機関やボランティア団体、民生委員などとの連携も図っています。
当協議会も、各地域包括支援センターと密に連携を図りながら、様々なご相談に対応しております。
Q5. 離れて暮らす親のお金の管理が心配ですが何か良い方法はありますか?
A.
認知症などにより、離れて暮らす親族に判断能力の衰えが見え始めたときに活用できるのが、「地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)」です。全国で展開されているサービスで、窓口は全国の都道府県および市区町村に設置されている社会福祉協議会(社協)です。
公的介護保険のサービスで、提供事業所との契約が心配なときには、契約手続を援助してくれます。また、本人の代わりに「生活支援員」という人が預貯金の出し入れをしたり、通帳や印鑑、権利証などの書類を貸金庫で預かるサービスもあります。このサービスを利用することで、悪質商法からの抑止力になりますし、親御様宅を福祉関係者が訪ねることにより、安心度はアップします。
また、認知症の症状が進んだ場合は、「成年後見制度」を利用することも考えましょう。
Q6. 相続税がかからなければ、相続手続きは必要ないのでしょうか?
A.
相続税の申告が不要であっても、亡くなった人名義の不動産や預貯金等の名義変更など各種手続きは必要です。というのも不動産については令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。いくら、生前中の「相続放棄する」旨の同意や書類を作っていても、法的効力はありません。正式な『放棄』は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必須です。
詳しくはお気軽にご相談ください。
Q7. 遺言書が出てきました。不満があっても我慢してそのとおりにしないといけませんか?
A.
その通りにする必要がない場合もあります。
相続人である配偶者、子供、父母には、「遺留分」と言う最低限の財産を相続できる権利が与えられています。その遺留分というのは、法定相続分の1/2とご理解ください。(兄弟姉妹には遺留分はありません。)ですから、遺言で書かれた財産配分割合が法定相続分の1/2を下回っている人は、逆に、過大に相続することになっている人に対して不足分を請求できます。
しかし、配分財産内容に不満があるだけで、時価ベースでの配分割合が遺留分を満たしていれば、話は異なってきます。その他にも、デリケートな内容もございますので、まずはご相談ください。
Q8. 遺言書に財産が漏れていました。この遺言書は無効になってしまうのでしょうか?
A.
無効にはなりません。
しかし、遺言書に記載のない財産については別途遺産分割協議をする必要が生じてしまいます。遺言書の内容によっては遺産分割協議が難航する恐れもありますので早めにご相談ください。
Q9. 自宅を兄弟ともに相続したい意思がある場合どうしたらよいでしょうか?
A.
兄弟で共有することは法律的には可能ですがあまりおすすめできません。将来的に相続が発生するたびに共有者が増えていく可能性が高いからです。どちらかが自宅を全部相続して、自宅の価値の半分に見合う金銭などをもう一人に渡す「 代償分割 」という分割方法を検討することが多いです。
Q10. 丸ごとお片付けをお願いしたいのですが、対応可能でしょうか?
A.
もちろん大丈夫です。
現在、無許可業者による不法投棄や不適正処理が問題になっています。ご家庭のごみや不用品を回収するには、 行政の「一般廃棄物処理業許可」が必要です。許可を受けている会社様同行の下、まずは無料でお見積りにお伺いいたします。遺品整理などについても、真心こめて整理させていただきます。
Q11. 不動産を売却する際の諸経費はどういったものがあるの?
A.
主な物は以下のとおりです。
• 仲介手数料(成約価格×3%+6万円に消費税を加えた額)
※売買価格が400万円以上の場合
• 抵当権等抹消費用
※抵当権等が設定されている場合になります。
• 印紙代
※印紙代は売買契約の価格により異なります。
• 測量代、境界設置費用
※敷地の境界が不明確で境界標の設置が必要な場合
必要な諸費用は、物件により異なります。実際に何にどのくらい費用がかかるかにつきましてはお調べいたしますのでご相談ください。